いま、人生の黄昏時も過ぎてもうちょっとで物のあやめも分からなくなろうという時期になってふと、じゃなくてもちゃんと思い返してみると
まず与えられた自然環境が自分の心の一番の基礎を作りその上にその時の社会環境やらがちょうどサザエが次々に殻を伸ばして体を大きくしていくように成長して行ったように思える。
戦争の時代に生まれたが戦時の記憶は夜空に陰々と響く空襲警報のサイレンの音と「寝床に靴履いて入っていなさい」と言った親の言葉、うちの中なのにそれも布団の中に靴履いて?という違和感だけが
記憶に今でも残っている。
見事に我が家は丸焼けだったがその焼け落ちた廃墟の記憶はまるでない。
終戦の次の年の4月入学、教科書はまだ新しいものができず先生が「何ページから何ページまで切り取りましょう」なんてマッカーサーが文句言わなさそうなところだけ残して古い教科書を使っていた。
占領軍におべっか使いたかったのかどうか分からないがこの小学校でずーっと「自分で考えて実行しよう」という個人主義が大事だと教わって六年までいたからこれが思想の根っこになったのは間違いない。
武蔵野のそれも端っこにあった家は疎開先が丸焼けになったのにこっちは焼夷弾ひとつ落ちなかった。家の隣は武蔵野の野菜畑が広がり家の後ろに林と呼ぶのは大胆過ぎないかい?と言われそうな雑木林があって友達と鬼ごっこ(戦争中の名残か鬼ごっこって言わずに戦艦ごっこって言ってたなぁ)をしていない時はその林の中でじっとしているのが好きだった冴えない子だったらしい。
しかしこの記憶が高校生になって目を覚まし北アルプスの雪渓の写真をみて「この景色をなんとしてもみたい」と思うと山岳部へ。
山岳部、今おもうとあれはまさに若衆宿そのものでしたなぁ。下っ端から順番に重いものを担ぐ、縦走合宿の前には体を「慣らす」ためと称して2を背負ってマラソンをしやっと帰ってくると今度はそのまま蛙飛び。
ほんとに死ぬかと思ったが経験するということはすごいものでこれが後で自衛隊で役に立った。マラソンだって自衛隊のマラソンは速さだけじゃなくて一人も落伍者を出さないで全員完走が基本、足がつったり気絶したやつは何人掛で担いで走る。不思議なことはここはまるっきり若衆宿ではなかったですね。私的制裁厳禁は共通語で銃の手入れが雑だったり制服のズボンの筋目がよれたりしていると「はい、営庭3周」で体力向上に役に立つことが罰だった。張り飛ばされるなんてことは全くありませんでしたよ、今も変わっていないだろうなぁ。
でこのふたつの経験がボーズへの道に進む元気のもとになったのですがこのボーズトレセン、これはまぁ徹底的に若衆宿でしたなぁ。同じ僧堂でいた時間の長さだけで身分の上下が決まり目上の人には絶対服従
体罰は日常茶飯、と言っても傷が残るとまずいので平手で張り飛ばす。目から人よく物の例えで言いますが’ほんとに張り飛ばされた一瞬あたりぱっと明るくなる。意地クソの悪い旧参(先輩のことですな)は
寝ることを邪魔する。夜座と言って正規の座禅の時間に他にまぁ今時の言い方なら自主研修と言いますか、夜開枕(消灯のことです)になった後こそっと本堂の縁側とかに行って(まるっきり外だと夜露で体が濡れるでしょ)自主的に座禅をするわけですよ。
この時1時間ぐらいすると上位の人から順番にこれもこそっとかえってねる。寝るんですが自分より上位の人が寝に帰らない限り帰れない、が意地悪は席を立ったのに下のものが気が付かれないようにこそーっと立つ、気がつくまでに1時間2時間。ね、意地クソ悪いでしょ? 誰かが今の世の僧堂の暮らしは二百年前の農家の暮らしそのものだ、という人がいたが庭に出て掃除するのもゾーリなど勿体無い、裸足でやれなんて。藁ゾーリだって自分で使っては勿体無いという暮らし、江戸期の農家のねぇと思った物でした。
でそんなこんなしているうちに外から苗木屋の店に並べられた鉢の枝ぶりがいいやってんでお客さんがつくように「うちの寺へ来ておくれ」というお誘いがかかるんですがこの卒業判定がまず自分が「もうそろそろか」と思うことと僧堂の指導者老師が「うん、年も年だし世間に出してもいいか」と思うことと出家した時に得度した(頭を剃った』授業師の三人が合意しなければなりませんのですよ。
システム的には誠に人間の内面の成長を支える騒動らしいシステムなんですがパソコンだってプロが設計するのにバグが出る、ボーズも同じです。
今日はここまで続きはまたね。まだ飽きがきません?
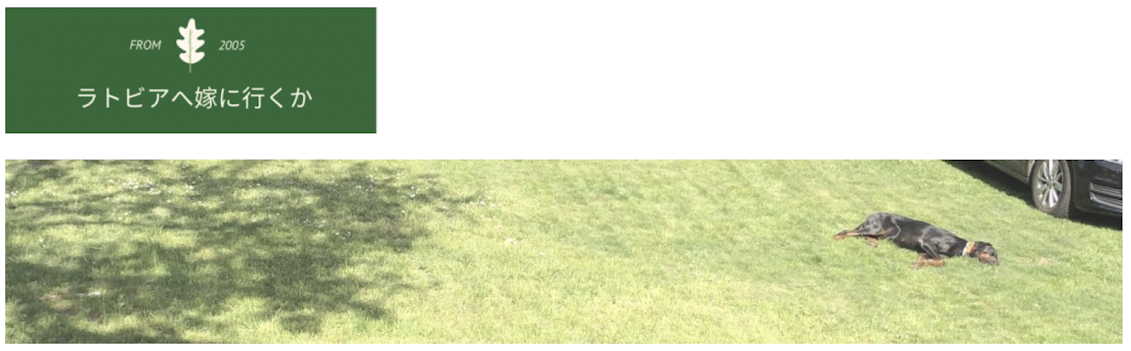
8 件のコメント:
さんさん 全然飽きませんよ。読み進めば進むほどにこの先がまた気になるものです。
さんさんが鍛え上げられた過程は今ならハラスメントと言われてしまうことばかりです。
今、こういうハラスメント類に声を上げる人が多くなってきて、それはそれでいいことです。
でもハラスメントが批判されることによって萎縮してしまい鍛えられる機会を奪われていることもありそうです。
さんさんのお話を読んでいるとお坊様の世界も人間の世界、今度の法事の時にさんさんのお話を思い出してしまいそうでどんな顔してお話を聞けばいいのでしょう。
さんさん様、菜の花の沖3巻読み始めました。儀式、習慣、必要悪。どれを取ってもこの時代にいたら受け入れているのでしょうが、今に生まれていてもイジメからは逃げられていないのも事実。司馬さんが言う文化でも納得はいかないし嫌なことをされたくも、したくもないです。
私は祖父を思い出します。戦後産まれた子が立て続けに育たず、ある時悩みを打ち明けたお寺さんに信心していないからだと説教され、心を入れ替え信心したら子が助かった話を子供のころから聞かされていました。助けてくれた法華経に最後まで助けてもらっていました。しかし生前もらっていた戒名を使うことをお寺さんに母が伝えたら、自分がつけたものでないから困る、ま、戒名料出せばうちでつけたことにして使っていいよと言われた話を後々聞いたら、あの世で祖父がどんな顔をしただろうとため息が言う出ました。そのお寺さん、戒名の件快諾したと祖父から私の母も孫の私も聞かされていたので、まぁガッカリでした。長くなり申し訳ありません。
さんさん様。まだまだお話楽しみです。菜の花の沖も。
さんさん、どうしたんでしょうね。
多分、ネットに繋げられていないとかそういう状況なんだと思います。トンガの火山爆発があった頃ぐらいからメールにも返信がない状態です。さんさんのことなので、きっとひょろっとやってきて饒舌に色々語ってくれるんだろうなと思うばかりです。
待ってるよー、さんさん!
ごめんなさいごめんなさいって私が謝ったって役に立たないんだけれどポツッて投稿をやめてそれっきり一月近く音信不通、こりゃ読んでくださる方には気になりますわ、まったく。びょうびょうと遥かな高みを吹きすぎる風の中から「こりゃくたばってるな、間違いなしじゃ」とか「あいつ残ったからマトモな死に方はしているまい。高いとこから落っこちたら下に尖った杭が」はマトモな方で「大方強盗にあってくびり殺されたのに違いない」なんてすごい声が聞こえてきた…様な気がしましたがなんのことはない木が倒れての断線とそのショックでパーツが壊れたのに部品が手に入らない、ただそれだけのことに一月近い時間がかかったわけ。これいうと日本の友達から「ちょっと聞くけれどオーストラリアってアフリカのどっかだった?」なんて混ぜ返されますが自動車パソコンからマッチ、トイレットペーパーまで自分で作らないで輸入に頼る、植民地時代の影が21世紀に至っても後を引いている、それに加えて金は欲しいが働くのはイヤってしょうもない癖が競争相手がいないために蔓延っている。
まぁその代わりに群青の青空と朝から晩まで小鳥の鳴き声が絶えない環境が手に入る、さぁどっちがいい?と聞かれると「う〜ん」と言わざるを得ません。
ネカフェってものがあるでしょうが?と言われましたがあそこのpcは日本語のソフトが入ってない、当たり前ですが。お返事を英語で書いったって「何これ?」と言われるのがオチ。日本語のニュースも読めない有様。
今日こそは、今週こそはと思いながら皆様にご心配をおかけしていることを気にしつつずけた
時間でありました。
やっぱ何年経っても根は私も日本人なんですねぇ。
どうかもう風が吹きません様に、だいたいあのユーカリって木はアホーと言ったら怒るでしょうがどのくらいの太さになったら枝が自分の自重を支えきれなくなって折れるか考えもしないで太くなる癖がある。おかげで年に何回か「折れたユーカリの枝に打たれて人死にが出た」なんて記事が目につきます。公園で人が死んだら補償金は税金で賄われるんだろうか?
紫陽花さま、megmegさま
長い間音信不通ですみませんでした、上のコメント欄に書いた様に簡単な理由だったんですが皆様にご迷惑おかけして申し訳ありませんでした。
菜の花の沖、私も改めて読み終わりました…三巻目あたりまでは嘉平さんという人物の魅力に惹かれて順調に読めましたが以前は気にならなかっら著者の”解説”というか時代の背景の説明が
4、5、6と巻を進めるに連れて量が増え「わかったって、あなたがよく資料を読んでいるのは!」と反感すら覚える始末。なにしろ文化勲章受賞者に反感ですからねぇ我ながら無謀だとは思いましたが。
と思ったらちゃんと書いてありました「…いわゆる嘉平物語を書くことよりもその時代の海運と背景にある日本の経済そしてそれを取り巻く世界の方に著者の興味はある」って。
なにしろ五巻目になると嘉平という名前は400ページほどの一巻の中で380ページごろに一回出てくるだけ。
まぁ以前は気にならなかったことが気になる、これも歳のせいでしょうか。
そうそ思い出した。
菜の花の沖の中に日本社会の一番基礎の基礎、根っこの先のところにあるのは「意地悪する」
という思想ではないか…と書かれています。
先輩が新人をいじめる、折れない程度に気を使いながらとことんいじめるのがめんめんと続く日本社会の基礎なのではなかろうか、いや無かろうかじゃない”なのだ”と断定して書いてあったかな?
松の廊下の刃傷沙汰も新しく役についたものを先輩がいじめるというパターンだし復讐したら文句なし全員死刑という判決だって”おかみ”もいじめが社会に蔓延しているという認識で放っておいたら何がおこるかわからないと言う事だからでしょう。
いまだに忠臣蔵が人気があって興行会社はあれがなければ歳が越せないと言うのも社会の根のところは変わっていないと言う事?
コメントを投稿