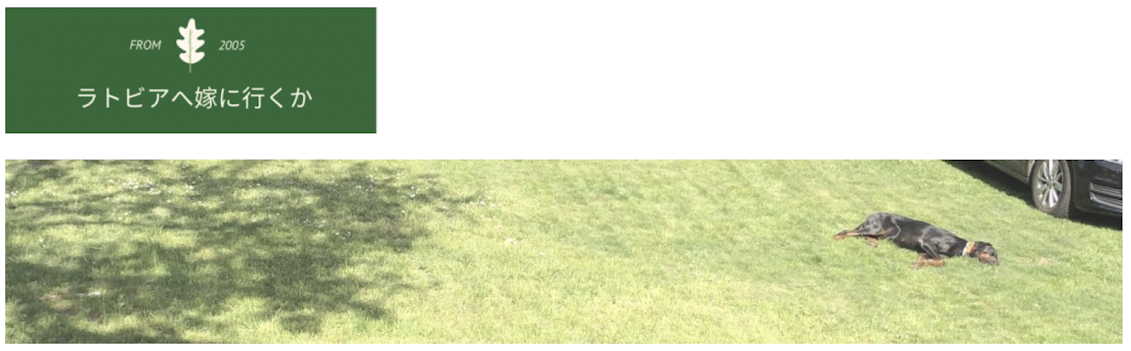無事手術と一泊入院を経て帰還した管理人である。
黄斑前膜(もしくは網膜前膜)の手術はあまり体験談を見かけないのと、やはり自分のための記録として記憶が鮮明なうちに残しておこうと思うのであった。
さて、手術当日は朝9時から病院で術前検査である。
検査項目は主に目に関するものである。検査待ちの時間に気づいたことは、眼科というのは想像以上に高齢者ばかりだということであった。管理人は最も若い部類に入るのである。それが11時ぐらいに終了して入院する病棟のベッドで待っているとお迎えが来ると言う仕組みである。手術病棟へ行く前に何やら注射を腕とお尻に受けて、その後手術着に着替えるのだが、なんと紙オムツ着用なのである。手術病棟まではなぜかスタッフが車椅子で運んでくれた。結構遠いのでど近眼が裸眼で転倒でもしたら困るということなのかもしれない。
手術室の前の椅子で待っていると、手術室付きの看護師さんが定期的に目薬をさしてくれた。そしていよいよ手術室へGOである。
黄斑前膜の手術には3段階ある。
- 白内障用レンズの装着
- 眼球上に手術用ポートの設置
- 硝子体の除去と代替液体の挿入
- 網膜上に張り付いた膜(これは硝子体由来)を染色してピンセットで剥がす。
である。そしてその前に目の下の若い女子で言う涙袋のあたりに麻酔の注射を打つのであるが、これが地味に喉の奥の方でケミカルな味となって認識できる。ラトビアラジオ1の流れる手術室内でしばらく待っていると麻酔が聞いたらしく瞼が痺れたような感覚になった。その後は左眼の部分だけが開いているシートを被せられ、まっすぐ正面に見える光源を見ているように言われて、いつの間にか目を開けっぱなしにするような器具がいつ装着されていたのであった。
執刀医は女医さんで、とても落ち着いた穏やかな声で色々と声をかけてくれた。
「ちょっと、嫌な感じがしますよ」
という前置きで行われたのが1の眼球上に手術用ポートを設置する、と言うやつである。つまりは白目の部分に注射針のようなものを3箇所突き刺すのである。その注射針のような中の空洞に手術道具を通して遠隔操作で眼内手術を行うのである。つまりは腹腔鏡手術のような感じである。さて、その感じはというと、大変恐怖であった。局所麻酔が効いているとはいえ、目玉に針を3本も刺すのである。その時の圧と言ったら、ちょっとではない、言いようのない嫌な感じMAXであった。
ちなみにここまでの行程では何が行われているのか想像はできても実際に見えるわけではない。痛くない、そして目の前はぼんやりしていて手術は見えないと言うことが安堵につながるのである。ところが、しばらくすると何か線状の物が見えてくる。それはどうやら何かを吸い込んでいるようである。これが行程の2番目の硝子体の除去である。そして驚いたことには、青いインクのような液体が注入されてくるのもはっきり見えるのである。さらにしばらくするとピンセットのような道具が出てきて薄い青色に染まった膜をつまんで剥がし始める様子もくっきりはっきり見えるのである。これはおそらく、普段は真っ暗な眼球内に光源を挿入したからなのだと思うのである。その光源で照らされた場所の網膜に眼内で光を浴びている物体などが映し出されているのだと思うのである。だが、本当のところはわからない。
青く染まった膜をきれいに取り除くと、剥がした青い膜が目の中の液体の中をふわふわと漂っている。それを時折吸引機で吸い込んで除去する。全部剥がし終わってから眼内の液体を何回か交換するとどうやら眼内作業は終わりのようである。正直、白内障用のレンズはいつ装着されたのかわからなかった。
そして最後に白目部分に突き刺さっている3本のポートが抜かれた。そしてどうやらその抜いた部分を縫っているような感じであった。
縫うのか。。。眼球を縫うって。。。
局所麻酔のおかげで縫い針で縫われていると言うような感覚はない。だが、とにかく最後に糸をギューっと結んでいる感じなのである。それを3箇所である。
看護師さんに誘導されながらまた車椅子で病室まで運んでもらったのであった。「病室へ戻ったらお昼ご飯を食べて、横になって3時間ぐらい寝てくださいね」と言う看護師さんの言葉通り、すでに昼食が用意されていて、それを食べると一気に眠くなって3時間ほど眠った管理人である。