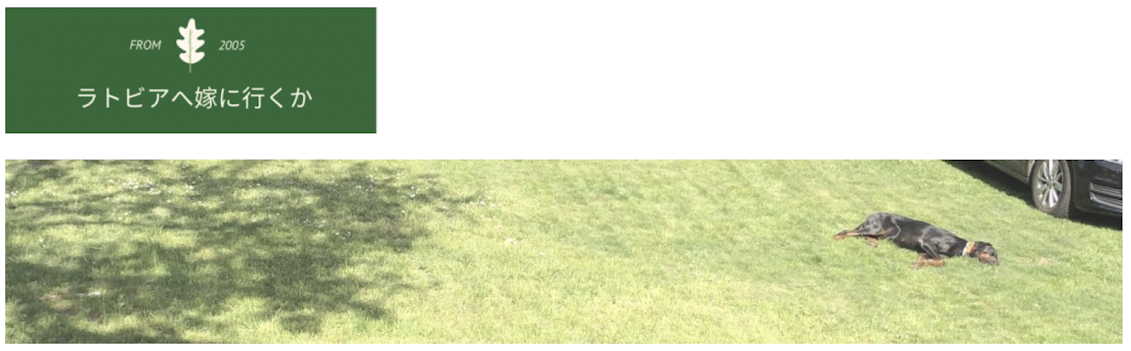ゼリー寄せというか煮凝りというか、は旦那の大好物である。通常、我が家ではクリスマスやイースターなどに豚肉や牛肉で作るのが習慣なのだが、時々旦那がちょっとお高い惣菜屋で鶏肉のゼリー寄せを買ってきては朝食にしているのである。というわけで自作してみることにしたのであった。
材料は
鶏ドラムスティック 1kg
ローレル等香辛料
塩コショウ 適宜
である。
これらのものを電気圧力鍋に入れて、ドラムスティックにかぶさるぐらいの水を加えて高圧20分自然リリース、である。
ドラムスティックから骨とか皮とかを取り除いてほぐし、細かめのザルで越したスープに戻し、ゼラチンを加えて冷やし固めるだけである。
 |
| 右下、ヒタヒタの水で煮る。上、骨と皮を取り除いてほぐしたもの。左下、ゼラチンを加えて容器に入れた状態。これを冷蔵庫で冷やし固める。 |
なんでまた作ろうと思い立ったかというと、ドラムスティックが1kgで3.4ユーロという特売に遭遇したからである。骨付き鶏肉は安くてお手軽に大変美味しい出汁が取れるのでゼリー寄せにはもってこいなのである。