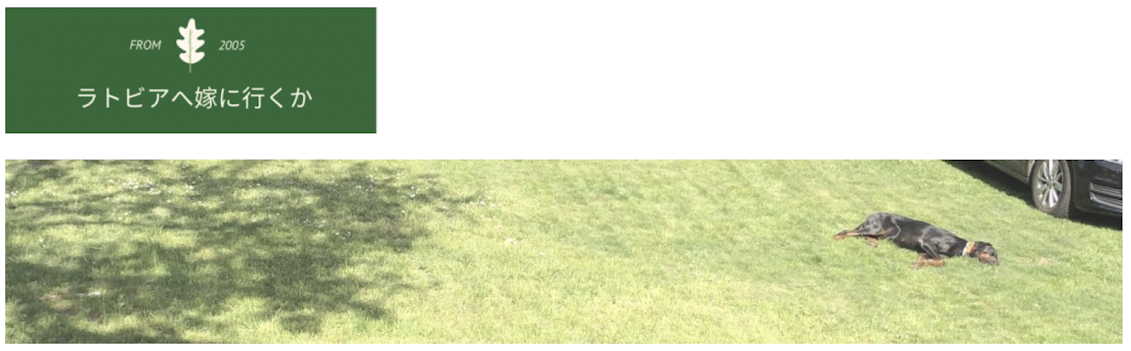今朝もマイナがお腹を空かせて木の枝に泊ってこっちを見ているのでご飯を投げてあげたら
「ありがとね、でもあたいらがベジタリアンだって言っていたの聞こえなかった?」っていうので
「マイナ語でピロピリ木の上で言ったってわからないさ。まぁこれからはごはんあげるよ」というと
「うれピィ、でもさぁ出来たら冷蔵庫に入れてあった昨日のご飯じゃなくて炊き立ての方がもっと嬉しいかも…」と申しますので
「あのな、おめさん達の言葉しらねぇけどよ、人間の方じゃそういうの”わがまま言うな”っていうんだぜ」と申しますと
「やだぁ、これでもないよりマシ」と言ってきれいに食べてしまいました。
常連の鳥達を見ていると一人一人性格が違うのがわかり始めました。
止まっているところから大きく動かずに咥えられるところに放ってやらないとパスする横着なやつ、顔を並べて餌を突き合う友好的なやつも反対に自分より体が小さいと「おう、ここは俺っちの縄張りだゼェ」と嘴をカチカチ言わせて威嚇するやつ、ほんと今までは小鳥という一括りで考えていたのが申し訳なく思います。
英語国民が庭の鳥までジョージとかメリーアンとか個別に名前をつける癖があるのはこういうところからなのだなぁ、と。
わがまま言っちゃ行けねぇぜ、と言った途端に思い出したんでございますよ。
僧堂にいた頃毎朝麦6コメ4の雲水のご飯とは別に小さな一升炊きの釜で混じりっけなしの白いご飯を炊いて
おクドの上に祀られた三宝荒神から玄関を入ったところの大黒様そして本堂に5ヶしょ位牌堂の大日如来に3ヶ所さらに開山どうに…おっと忘れた老師の時念仏と露座の観音様も
御仏飯をあげるのが決まりでしたがその時に大先輩から佛飯てのはなぁ大自然に対して「ここに居でさせていただいてありがとうございます」って気持ち捧げなあかんでって言われたことを思い出しました。
大自然に感謝といえばこの庭に来る鳥へのご飯もやはり御仏飯と同じだから昨日のご飯じゃ気持ちが通じない。
で持って鳥に言ったんですよ、わかった感謝が足りんかった、これからは炊き立てをあげるから、ただしわたし所は二日に一回しかご飯炊かないから
炊かない日は生米を盃にいっぱい出して置くからそれで勘弁ね、って。
この炊かない日は生米をちびっとってのはこれも僧堂の知恵、いかに僧堂でもご飯を炊かない日もある、そんな日は生米ちびっとでお参りに来た檀家さん対策をする。
ボーズと政治家という人種は本当に言い訳が上手ですね、いやほんと。