今、司馬遼太郎の「菜の花の沖」という本、さぁ何度目の読み返しになるだろう、四回目か五回目かどこかそのぐらい。
主人公の嘉平という男、淡路島の最北端のそのまた先にある小さな島に生まれてその島の中で本村という部落、この部落という概念はいなかに住まないとなか中しっくりできないモノですが都会で言えばなんとか町何丁目ぐらいの大きさと言っていいでしょうか。
本村で食べるのもやっとのビンボー暮らしの家に生まれて12、3歳で親類の雑貨屋の家に住み込み奉公に出る…動機は親に食べ物の心配をかけないように、ってんですからそのビンボー振りが分かる。
で今でもそうですが特に田舎では青年団,若集組ってものがあって参加はほぼ強制だったらしい。こういう小さい集団ではビンボー人の子はいじめられますが彼は思うところがあって奉公先の部落の若集組に加わらず生家のある本村の組に入った。これはいじめの対象になりやすいですよ。おまけに部落一の美人さんが彼に惚れた。もう止まりません、若集組の中のおっちょこちょいが嘉平に浜に干してあったいりこを盗んだという濡れ衣を着せて叩き出す仕掛けをした。
嘉平はこの小さな淡路島の脇の小島のその中の部落という共同体のそのまた若集組という一部の人たちに憎まれた自分という事実に納得がいかず彼は瀬戸内海を渡って対岸にある明石だったかな、の廻船問屋に雇われて船乗りという海と風と船をどう釣り合いを取って走らせるか,という船乗りという技術者として生きる道を選んだ…というのが長々と続く菜の花の沖の第一巻のあらあらとした内容なんですが
この中で集団の中に身をおいたらどれほど非合理と思われる決定や習慣でも「はい」という以外の返事はできない。
自分の頭で周囲の状況を知り判断して自分の行動を決めることが許されないし一度参加した組という小集団から抜けることも他所の組に移動することも許されない。
小学校に入った時から自分の頭で判断しなさい、自分が決めたことはその結果がどうあろうともその結果を受け入れなさい…てな事を聞かされて「それが個人の自立というモノです」と聞かされて”うん、これだよこれ、と思い定めて私は大人になったんですよね。
ところが自分で情報を集めて自分で判断して決心したら歯を食いしばって実行して結果に責任を持つ、ってこれが日本の世の中では通用しないってことがわかるまでにそう時間はかかりませんでした。
これは楽しようとして社会の本流であるサラリーマン、営業なんてところに身を置いたからだろうと持ち前の好奇心を働かせて自衛隊で鉄砲打ってみたり(素質があるってんで狙撃兵に選ばれて射撃の集中訓練までしましたっけ)その後坊さんならどうだろうってんで見ず知らずのお寺、東京生まれで四国なんて行ったこともなかったのに高知の町外れの見るからにボロ寺。
「あの私僧侶になりたいんです」
「そうかまぁ上がってしばらく居てみな」
このふたことだけでこの寺の小僧になってしまったわけでその後歩いて四国遍路回ってきなさい、と言われて歩き遍路。何しろ金持たずで托鉢していただけたら飯食えばいいし何もいただけなかったら飢えればいい、それが修行じゃぁ」っていわれて”はぁーい” ひとまわり千六百キロでしたか3、4ヶ月かかりました。お金がある時は遍路宿って安宿で、ない時は村はずれのお宮さんの軒下とかで野宿、要するに今風にいえば歩きホームレス暮らしですなぁ。
しかし伝統というものはすごいもので白衣で杖をついて歩いているとこちらから願わなくてもお米とか10円玉(何しろ五十年以上昔のことですから)を胸にかけた頭陀袋に入れてくださる方がいる。道連れになったお遍路さんにも「もうじき癌で死ぬからどこまで行けるか知らないけれど行けるところまで」って言われる方や「破産して首吊ったけど死ねなくてねぇ」なんてすごいこと言う人も。
もちろんルンルンでご夫婦でハイキング気分で歩く方もいらっしゃいましたがそれもこれも混じりあって流されてゆく社会というモノを感じました。
この辺で「よし。本気出して禅坊主になろう」と言う気がむっくり湧いてきたんです。
で帰ってきて…なりたいって和尚に言いますと
「よし、三年は暫暇(業界語で休暇のことです)なしで僧堂で居りっぱなしで居ろ」と言うお言葉、そのまま頭丸めて何やら色が変わった先輩が残した木綿衣や脚絆を身につけて、パンツまで褌にされたなぁ、四国から海を渡って天下の鬼僧堂と言われる久留米の修行寺へ。そこでまる五年いて和尚が亡くなってから後住、後つぎの住職ですなが決まらんでもうう何年も人が住まない寺があるから来てちょうだい、といわれて。明治の何年かに初めてできた新しい寺で私で8代目。
と言うところで長くなりました今日はこの辺で。菜の花の沖と私がどう重なるかは次回のお楽しみ。
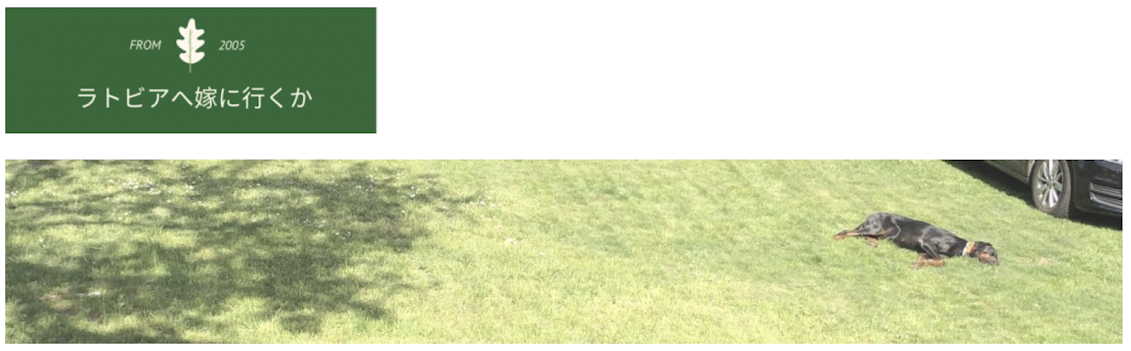
5 件のコメント:
読むからには最後まで読みたい願望があるので、司馬遼太郎の本は長すぎて読破出来ないので避けてました。したがって菜の花の沖も読んでいません。さんさんのあらすじのここまでの内容を読んでいると、現代の日本の企業やひょっとしたら官公庁だって未だにこんな感じ。根本はちっとも変っていないような感じです。
さんさんが殻を破ってお坊様になる道に入っていかれたこれからの続きを楽しみにしています。
今日は4年ぶりの積雪。帰宅時に滑って転んだと言って帰ってきた人が若干一名。万が一に備えての靴選びをせずに行ったので仕方がありません。
さんさんのお話、続きが気になって気になって〜!自衛隊の話が出てきたり、営業の話があったり、移住されていたり、どのような背景かお聞きできたらなぁと思っていたのです。
どなたでも伺うと波乱万丈、山あり 谷ありの人生をお持ちだと思いますが、さんさん様は思いもつかない道を歩かれていますね。
お体無理のないように、お話の続きをお願いいたします。
紫陽花さま、ほんとあの著者の本は第六巻とか全八巻揃いとかめっちゃ長いものが多い感じがします。兎角一つの物語が長々と続く、特に伝記物で長いものは一つのシーンの背景描写から主人公以外の登場人物の心理描写まで丁寧に描きすぎて「わかった、もうそれはいいよ。で、どうしたの」とまだるっこしくなって本を読むのをやめたくなって「いやいやここまででももう2000円投資してるんだから…」って葛藤を計算にすり替えて読み続けたり。
司馬遼太郎の本も坂の上の雲にしても長いですよね、しかしこの方のはストーリーの構想が雄大であるせいかあまり退屈しない、最後まで引っ張ってゆく力があるように思えるのはやはり筆力というものでしょうか。
megmegさま
続きが気になって…とおっしゃっていただける、ありがとうございます。
あっち飛びこっち飛び”なんデェ、ただのわがままモンが一丁前な顔してあっちこっち食い散らしてるだけじゃねぇか”なんて言われてもしょうがないんですがただ八十うん年間必死で目の前に出てくる問題を片付け片付けしながら例えてみれば生きの良いアジがえらい安く手に入った。さてこれをどうしたら一番”満足感”が大きくなるだろう…と考えて今夜は叩きで、残りは開いてひと塩にして一夜干し、明日朝は焼いて食べましょう。それでも残るなぁ、買いすぎたかや?
じゃぁ明日の夜は干したのをそのまま唐揚げにしよう、もしかしたら骨まで食べられるかも。
なんて思いめぐらせ行動してきた生涯でした。
最後移住後には何を飯の種に?
あっとおどろくためごろぉ〜…いい加減にせいや、古りぃってんだよっ。
菜の花の沖、読んでみようと思います。
あっちこっち、流されず問題解決にまい進されたのはすんごい事ですね。すごいじゃ足りない!
上橋菜穂子、ファンタジーと言われてますが人間の生き様の物語です。職場の先輩に教えてもらって、どんどん読んでしまいました。アボリジニの研究者でオーストラリアに長く関わっている方です。
老眼に乱視でショボショボですが、やっぱり読書はやめられない(笑)
コメントを投稿