今日はねんきん定期便のお知らせメールを受け取った管理人である。
まだ年金受給には何年もあるが、お知らせがきたのならそれなりに気になって確認してしまった管理人なのであった。お知らせメールには、
「ねんきんネット」トップページの「利用者情報」に表示される住所をご確認ください。表示される住所とお客様がお住いの住所とが異なっている場合には、このメールの下にある「ねんきん定期便」「ねんきんネット」に関するお問い合わせ先又はお近くの年金事務所にご連絡ください。
とある。確認したところ、管理人の住所は違っている。それで連絡しようかとお問い合わせ先を確認すると電話だ。メールじゃ無理、ネットでの訂正も無理。電話しろと。
だが、管理人は知っている。そんなところへ電話しようものなら案内録音が流れてきっと長い間待たされるのであろう。国内なら良いだろうけれども国際通話でそれをされるといくらかかるかわからない。
やあ、オッケー。まだ年金受給開始までにはしばらくある。このまま放置決定である。
さらに、今日気がついてしまったことは、年金受給開始の手続きには戸籍謄本か戸籍抄本が必要だということである。海外在住だと住民票がないからである。(この記事を書いた後に、戸籍抄本ではなく在留証明で良いということがわかりました。ああ、よかった。)すると、戸籍抄本とかはどう取るのかというと、自治体ごとに対応は異なるが、直接本人が郵送で取り寄せることになるわけである。ある自治体では
「日本に居住している親族に頼んでください」
とか書いている始末である。
それは凄まじく煩雑な手続きを踏むからである。
例えば、戸籍抄本を取り寄せるためにはその発行手数料と送付にかかる料金がかかるのだが、クレジットカード決済はできない。日本円の現金のみ受け付けて、お釣りがある場合は日本の切手で返送という具合である。
日本国内ならマイナンバーがあってそれを記載すれば戸籍抄本など必要ない。
もう、ため息というより調べていると胃が痛くなってくる話ばかりである。
というわけで、今日は総務省の「ご意見」というところに、在外邦人にもマイナンバーを発行してほしい、という要望を出しておいたのであった。
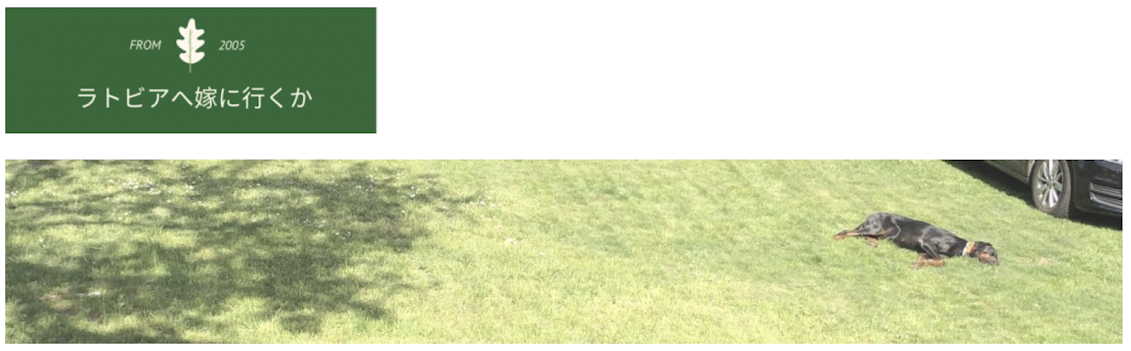
6 件のコメント:
管理人さん、こんにちは。本土にいても、面倒なお役所仕事。今はコロナ感染者が保健所からの連絡もらえず、どこに電話しても繋がらす、自分で判断して家にいろ、って自己判断できる人は少数派かと思われ、ため息です。とうとう自分の身近な人も発熱、検査はこれからですが陽性だったら差し入れに行かねば!
在外公館の発行する「在留証明」で十分なような気がしますが…
外務省と年金担当の厚生労働省はWHOの件(害務省の介入)等で仲が悪いからねぇ。
旅券の切り替え発行の場合、在留届の出ている公館での申請には、条件付きですが戸籍抄本は必要ないんでねぇ。外務省内部では問題無いようですが。
こんにちは、megmeg殿。
日本のコロナ感染者は急増してきていますね。これだけ急に増えると保健所も病院も大変ですね。ラトビアもまだまだ感染者が減りません。私も引きこもり状態です。
こんにちは、現役lecturerさん。
情報ありがとうございます。日本年金機構のHPの年金受給請求の必要書類で「全ての人に必要な書類」のところに戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか生年月日が確認できるもの、とあったので勘違いしてしまいました。そのページをスクロールして行くと最後の方に海外在住の場合は、世帯全員の住民票の写しに代えて在留国の日本領事館による証明、とありました。ほっとしました。まだだいぶ先なんですが何しろ全てが郵送でのやり取りというのがとても気が重いです。早くデジタル化して欲しいです。
再婚出産に関する民法の改正をする方向になりましたがなんと明治時代に作られた民法を今まで適用していたとは・・・触らぬ神に祟りなしなんです。実際に国民が困っていても馬耳東風。国際化が進んで国外で生活をしている人がどれほど困るかなんて気が付いていないのか気が付いていても知らぬふりをしているのか、どちらでしょうね。意外と気が付いていないのかもしれません。
電話で問い合わせというのは本当に嫌なものです。つながるまでに何回もブッシュしなければたどり着かなくて、たどり着いてもそれからつながるまでにまた時間がかかってうんざりです。不在通知が入って再配達を頼む時に自動対応の電話に入力しなけらばならない時もゾーッとします。
こんにちは、紫陽花さん。
その民法改正の話、私も日本のニュースサイトで見かけて愕然としましたです。今時、簡単に父親かどうかなんて検査できるのに、こんな法律がまだ使われていたなんて驚きです。在外邦人に関しては外務省は頑張ってくれている感じがします。先日もオミクロン感染の拡大で海外の日本人が健康不安を抱えている場合に無料で日本語の相談(要予約)ができるようにしたという案内が大使館から来ていました。大変ありがたいことです。
電話の問い合わせは、ああ、っていう感じですね。どうしてメールやらお問い合わせフォームで対応できないんでしょうね。
コメントを投稿