というのも、こんな日本から離れた地でも日本で見たことのある花とかつくしなんかも見かけるからである。
通常、庭や散歩途中で見かけた花の同定にはフィンランドのサイトを使っている管理人である。とても素晴らしく作られたサイトで花の色とか何枚花びらがあるとかいつ咲いてたかとかで検索できるのである。その結果、今日の花はクサフジだということになった。
 |
| なんとも言えない美しい紫色である。摘み取った時はもっと淡い色であった。 |
ちょっと写真では分かりにくいのだが、葉っぱがリーフレットという形になっていて、その
先端がツルになっているのである。これがマメ科植物の特徴で、この先端にツルがないとマメ科ではない。似た植物はたくさんあるのだけれど、これはマメ科である。
管理人の一押しのオレンジの芍薬のお供につんだのだが、芍薬より魅了されてしまう草藤である。
マメ科の植物と管理人の関係は深い。
小さい頃、まだまだ空き地がたくさんあった頃はシロツメクサがたくさんあって、その花を観察して、これはたくさんの花が集まっているのだなと幼心に発見し、そしてその一つ一つのはなが小さなえんどう豆のような鞘になるというのを見て感動したものである。カラスノエンドウも身近なマメ科の一つであった。大学の卒論のテーマはえんどう豆の光受容タンパク質であった。
なんだか初めましてのような懐かしいような、そんな雑草との出会いであった。
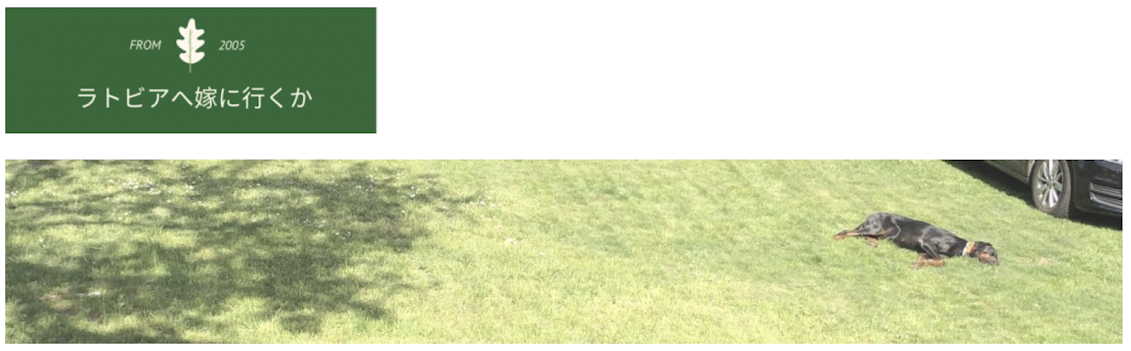
4 件のコメント:
久しぶりにコメントします。久しぶりなので自分のハンドルネームを忘れてしまいました。
年齢のせいもあり、いろんなことをすぐに忘れます。
管理人さんのお花の写真に癒され、料理の写真を見ると美味しそうなので食欲がわきます。
管理人さんの研究者としての視点で見る草花の考察を、そういう見方があるのか!と読みました。
そのオレンジ色の芍薬って私これまでの生涯でお目にかかったことがない。日本でもオーストラリアでもどちらの国でも約40年時を過ごしましたし私植物園大好き人間なのにみたことがない。
ラトビアではそこいらのお家に「わぁーッ」ってさいているんですか?
なんか管理人さんの文章では「お前は見飽きた花だから後で後で、暇があったら載せてやるかも。。。」って空気が伝わってきますが。
こんにちは、ゆのみさん。
ありがとうございます。励みになります。
ラトビアには勝手に生えてる綺麗な雑草がたくさんあります。春はそれらをみるのがとても楽しみです。日本も私の子供の頃にはたくさん雑草が生えていましたねえ。こんなに離れているのに、小さい頃見た植物を見つけることができるのが驚きです。
こんにちは、さんさん。
写真、記事に上げますね。ただ、へえーっていうほどのオレンジじゃないです。淡いピンクのちょっとオレンジ寄り、ぐらいな感じです。ラトビアの芍薬はクラシカルなものだと白、ボルドー、どピンクの3種類です。これらはどこのお宅にもわあーって咲いてます。ただ、ラトビアでは芍薬が庭に植えられる一番豪華な花なので変わり種も欲しくなって植えたりしてると思います。ただ、新しい品種はあんまり丈夫じゃないですね。
コメントを投稿